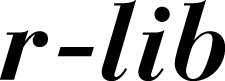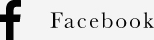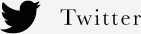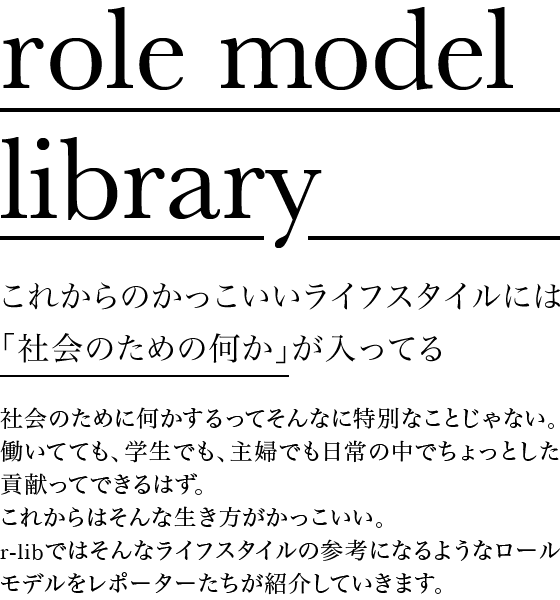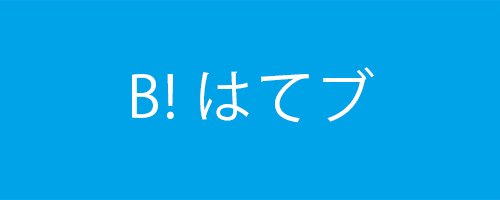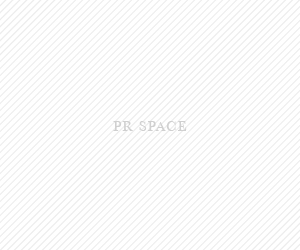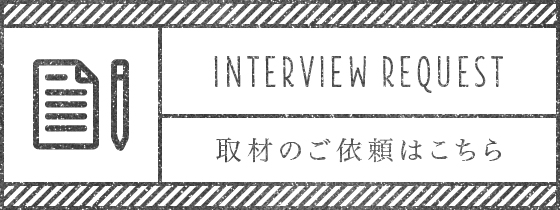# 009
DAISUKE IMAJO
October 08, 2014

GENRES 国際協力文化
国際協力文化
この近くで、遠くで、そして今起きていることーー
ソマリア、モガディシュの国境なき医師団の病院スタッフと今城さん。今城さんは、国境なき医師団では後方支援として医師や看護師の業務円滑のために奔走していた。
Reported by Editor Remi
難民問題の本質を伝えること
ー 確かにヨーロッパだと難民がいるというのが日常かもしれませんね。私も難民問題にそこまで詳しいわけではないのですが、多くの日本人がなかなかそういった情報に触れる機会ってないですよね。難民映画祭のおかげで少しでも多くの日本人がその情報に触れられるようになるといいですね。ではその難民映画祭で今城さんがされている活動の内容というのは?
プロジェクトの企画・運営です。準備から全てをまとめていくという作業をしています。映画を集める作業や、会場を手配したり、作品に字幕をつける手配などです。広報に関しては、ポスターやチラシは手作りなんです。元々雑誌の編集の現場で経験を積んでいた人間や、私も映画の宣伝を仕事としてやっていた事もあるので、そういう経験を持っている人間が集まっています。広報のもうひとつ重要な仕事が、メディアの調整というものがあります。イベントの告知に加え、難民問題の本質を伝えること、難民映画祭のために海外からゲストが来日する際のコーディネートなどもします。今回は『ボーダー~戦火のシリアを逃れて~』というシリア難民に関する作品の女優さんと、『スケーティスタン』というドキュメンタリー映画の中で登場する、スケートボードを使ってアフガニスタンの子ども達にスポーツの機会と教育の機会を提供するNGOの設立者が来日する事になっています。
全上映無料のUNHCR難民映画祭では先着順で整理券を配布している。会場で整理券を配布する今城さん
ー 映画関係のお仕事をされていたとのことですが、今のお仕事に至るまでの経緯を聞かせていただけますか?
はい。この仕事は今年で6年目なんですけど、それまでは独立系の映画の配給宣伝会社に2年間勤めていました。そこでドキュメンタリー映画の配給と宣伝をしていました。その前は映画とは全然別なんですけど、国境なき医師団というNGO団体に、それはだいたい足掛け8年ぐらい勤務していました。
ー 国境なき医師団ですか!!全然映画関係とは違いますね!!難民とは共通点がありそうですが。今城さんはお医者さんなんですか?
いえ私は医者ではありません。主にバックオフィスというか後方支援の仕事でした。1999年に国境なき医師団の日本の事務所に就職して2007年までいたのですが、その間ミャンマー事務所とネパール、スリランカなどにもいました。長い時は1年以上の滞在で、スリランカの津波の時は3ヶ月だけでした。津波が起きて翌日には現地に行って事務所を設営したり、現地の職員を募集して短期のチームが活動出来るような状況を作る、そういう後方支援の仕事をしていました。今でもたまにプロジェクトでハイチやソマリアなどに行ってお手伝いすることがあります。
最終的な目的は伝える事だけではなく、人やリソースを動かすこと
ー 最初に国境なき医師団でお仕事をされて、そこから映画にいこうって思われたんですね。全く違うジャンルですが、何か理由はあったんですか?
東京の国境なき医師団で働いていた時に、一番最初に任された仕事が広報アシスタントだったんです。人道支援の現場に行って仕事がしたいという気持ちが元々あったから働いていたのですが、常々感じていたのが、自分は医者ではないし、経験を重ねて色々出来ることがあったのでもちろんそれで良かったんですけど、途中からいったいどれくらいの人を動かせるほど影響を与えられているのだろうと考えるようになったんです。現地に行って仕事をして帰って来て、広報の仕事に協力して講演会でしゃべったり、レポートを書いたりしていましたけど、果たしてそれでどこまで多くの人に伝わって、人を動かす事に繋がっているのだろうと思ったんですね。やはり最終的な目的は伝える事だけではなく、人やリソースを動かすことなので。人を動かすというのはお金を動かす事だったり、人材がこのような活動に関わるように促すという意味で動かすということなんですが。じゃあそのための有効な手段って何かなと思った時に、最終的に色々考えた挙句、配給宣伝の仕事をやってみようと思って。ドキュメンタリーに限らず映画は元々趣味として好きだったんですけど。それで30歳過ぎてから転職しました。結構キツかったですけど(笑)。
毎年多くの会場ボランティアの方々の協力のもと運営しています。写真は各上映会場でボランティアスタッフに当日の運営の流れを説明する今城さん
ー キツいんですか?なんか前職のほうが危ない地域に行ったりしてキツそうなイメージがありますけども(笑)。
全くわからない世界に急に飛び込んだので。試写会で映画ライターさんやメディアの方にぜひこの映画を取り上げてくださいっていう、売り込んだりする仕事ってやった事なかったですからね。どうやったら扱ってもらえるかという事をずっと考えるのはそれまで培ってきた人道援助のスキルとは全然違かったので苦労しました。そこで2年間働いていた時に自分が担当したドキュメンタリーが、その当時の難民映画祭のラインナップに選ばれたので難民映画祭の存在を知ったんです。
ー ちなみにそれは何という映画ですか?
自分が関わっていたのは2本あって、1つは第3回難民映画祭で上映された『ウォー・ダンス』という作品で、僕が宣伝の委託を受けてやっていたんですね。ウガンダの子ども達が音楽とダンスをやるという作品です。もう1つはこれも同じく第3回難民映画祭で上映された『ビルマ、パゴダの影で』という作品です。すごくマイナーなドキュメンタリーなんですけど、少数民族の所にスイス人の女性の監督さんがカメラクルーを率いて、現地に潜入して撮影したものです。当時まだ今とミャンマーの政権が全然違う頃ですから、あからさまに迫害を受けていた時のものです。それが難民映画祭で上映されて、そのあたりから、ああこういうのもあるんだなぁと思い始めたんです。