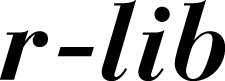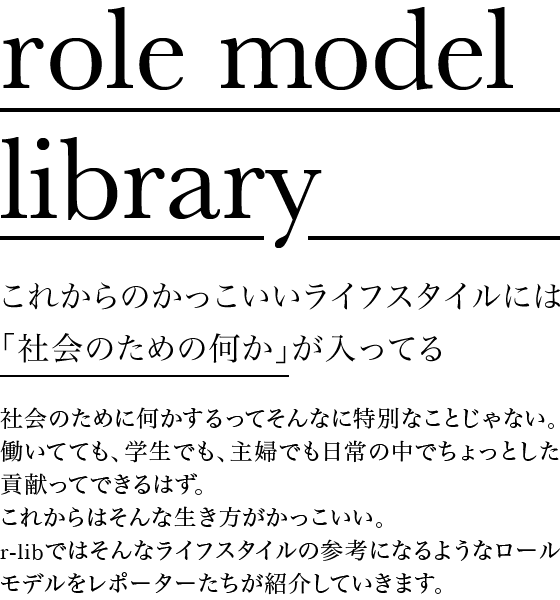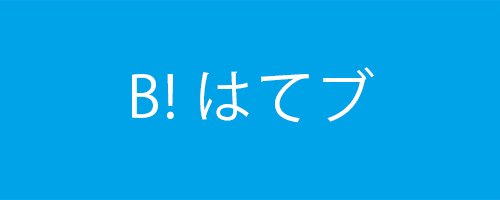5日目
トゥーンバの最終日。この日はバシャールの母親の聖書朗読に起こされることはなかった。いつもより遅く起きてきたので、だいぶ疲れているのかもしれない。
朝食後に、あの教会の仲良し家族の奥さんが迎えにきて、ゴールドコーストまで送ってくれることになっている。彼女は薬物依存症の更生施設で働いていて、夜勤明けにそのまま来てくれるということだった。
バシャールが、僕と久保田さんにお土産をくれた。ロンTとサファリハットだ。恐らくショッピングモールに一緒に行った時に、隙を見て買ってくれていたのだろう。そして、お腹が減るといけないからといって、バシャールの母親は、これからキャンプにでも行かせるのかというくらいに、何日分にもなりそうな食料を詰め込んでくれた。もう大丈夫と言ってもあれもこれもと追加する。絶対に食べきれないような量だ。本当にホスピタリティ溢れる人たちだった。
迎えの車が到着し、お別れの時がやってきた。バシャールは明るく別れを告げる。バシャールの母親は、あなたたちがいなくなると寂しくなるわという。再会を誓って僕らは出発した。
久保田さんは、こうやって何度も再会を約束して別れた友人たちを失っている。特にここ数年で15人ほど仲の良い友人が戦争で亡くなっているらしい。これが最後になるかもしれないという別れの挨拶は、彼にとって自然なことなのだろう。もしかしたら僕だって、この先の人生でバシャールと再会することはないかもしれないけど、そんなふうな実感を伴わずに別れの挨拶をしてしまっている。これが今生の別れになるかもしれないなんていう感覚は、普通はあまり持てない。
でも彼の場合、自分自身が数年後も生きていることを当たり前と思っていない。「絶対に生きて帰るとか思わない方がいい。死んでもいいやくらいに思ってないと」久保田さんと出会った頃、よくそんな言葉を聞いた。雑な表現に思えるかもしれないが、これは別に投げやりに命を軽視してるような言葉ではない。
実利的に解釈するなら、生きるための意欲が強すぎると、極限状況でパニックに陥って、冷静で合理的な判断ができなくなってしまうということなんだろう。今まで何人か戦場に同行させた人は、初めての銃撃戦で腰を抜かしてしまって、移動しなきゃいけないのにその場にへばりついてしまったらしい。こういう場合は死にたくないという気持ちが強すぎて、逆に死ぬ確率を高めてしまうことにもなる。
それは大前提として、それとは別に久保田さんの場合は、軽視とは違う諦観のようなものも感じ取れる。人の生死をたくさん見てきた人たちは、自分の命を客観視するようになるのかもしれない。自分の命を絶対的で主観的な視点でみることに固執せずに、俯瞰して捉えることができる。そのうえで世界を受け入れる。そこには一種の軽やかさがある。絶望と慈愛の間を漂う風船、そんなふうに僕は久保田さんの死生観をみている。そういえば「戦場で兵士は死ぬが、ジャーナリストは死なない、と思ってるのは勘違い。そんなに甘くない」ということも言っていた。
僕たちが何故ゴールドコーストに向かったかというと、サーフィンのためだ。久保田さんの趣味はサーフィンで、ここ最近本格的に始めたらしいが、とてものめり込んでいる。心身のバランスを保つにはとてもいいらしい。特に帰国したばかりで、まだ戦場にいる感覚のまま過ごさざるを得ない期間は、毎日のようにサーフィンに行く。
戦場でPTSDを抱えて戻ってくると、うまく日常生活との切り替えができないらしい。カッとしやすくなったり、花火が苦手になったり、日本にいてもいろいろと支障がある。そういう時に、サーフィンはセラピーのような効果があるということだ。だから失ったバランスを取り戻しに海にいくのかもしれない。そんなバランスなんてもう取り戻せないと彼は言うかもしれないけれど。
ゴールドコーストに着くとチェックインまでの時間も待たずに海に行く。波は全然良くないらしいが、待ちきれずに入っていった。こういう無邪気なところもあるのだが、普通の人の無邪気さとも少し違うように思えるのは、あまりに穿った見方だろうか。
6日目
今回の僕の取材目的は、彼の全体像を追いかけることだったので、僕も付き合ってサーフィンをすることになった。実は昔、湘南の海の家で働いてたこともあり、周りはサーファーの友達が多いのだが、僕はサーフィン初心者だった。夏は毎日海にいたというのにやらなかったくらい興味がないのだ。しかし板(友人のお下がり)は持ってるという正真正銘の丘サーファーでもある。
前日も、なかば冷めた目でサーフィンをする久保田さんを砂浜から眺め、請われてその勇姿を撮影するという感じだった。そもそも僕のような初心者が、こんな世界的に有名なスポットの波でやれるわけがないのだ。泳ぎも自信があるわけじゃないし、足つかないし、死ぬでしょと思っていた。ところが久保田さんの「死ぬかもしれないって経験したほうがいいよ」という一言で、僕は俄然やる気になった。
しかし、海に入って10分もしないうちに、沖の方まで流されてしまって、デカイ波が来るたびに板にしがみつくだけで疲労困憊。
これはまずい。岸に自力で戻るのは不可能じゃないか?あのライフセーバーの人たちは僕に気付いてるだろうか?という恐怖感がいきなり襲ってきた。死ぬかもしれないという経験は既にできたんで、今は本当に後悔してます、という気分だった。しかし、10分もしないうちに助けを呼んでギブアップなんてカッコ悪すぎる!と思って、がむしゃらに頑張った。なんとか無事に岸に戻れ、それ以降は慣れてきたので、特に恐怖感もなく楽しむことができた。
海に入ってる時や、休憩する時なども、久保田さんは僕がどこにいるかをしっかり見てくれていたような気がする。視線を感じるというよりは、相手の意識の中で自分が配置されてるような感覚だ。サッカーの試合でボールを持った時に、味方を直接見てなくても誰がどこにいるかぼんやりと空間で把握してるというあの感じに近いかもしれない。
結局、僕は一度立てた程度だったので、彼が感じているサーフィンの醍醐味が味わえたかというと、全然そんなことはないのだが、彼が頭を真っ白にして向き合うものを体感できたのは良かった。
久保田さんは、仲の良い友人を何人も看取ってきた。病気や老衰でもなく、さっきまで普通に話していた人が、自分の腕の中で死んでいくという経験とは、どうしたらうまく付き合っていくことができるのだろうか。これは久保田さんに限らず多くの戦争経験者たちが抱える問題でもある。この問題に関しても僕はやはり陳腐な考えしか浮かばない。こんな暮らしを20年以上も続けるなんて本当に想像を超えていて、久保田さんの普段の無邪気な感じは、悲しみや絶望を人に見せないように振舞っているように思えてならない。
そして、今回、その原点ともなる場所にも同行することになったのだった。
 国際協力
国際協力