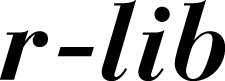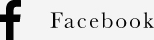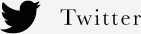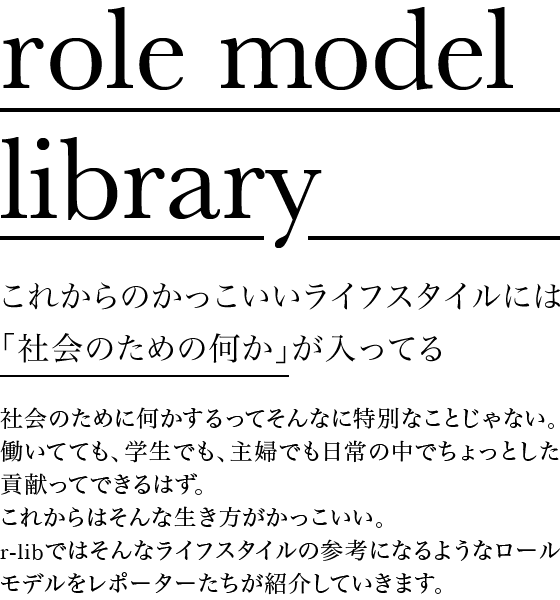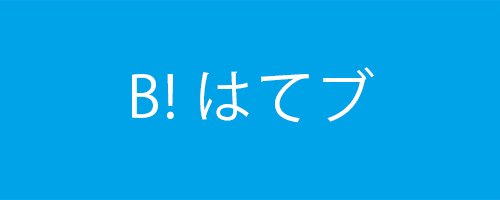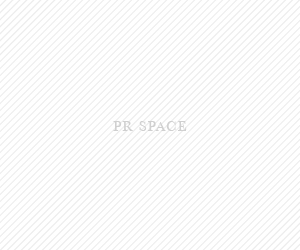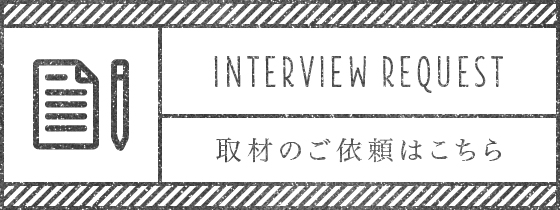# 018
SCHOOL OF BABEL
January 13, 2015

GENRES 教育文化
教育文化
世界の縮図のような多文化学級〜バベルの学校〜
24人の生徒で20の国籍という多文化学級の適応クラス。この適応クラスはフランス社会に馴染めるように、基本的なフランス語を移民の子どもたちに教えるという教育プログラムの一環だ。
Reported by Editor Remi
れみ
議論と言えば、映画では宗教などいろんな問題に対して、子どもたちが活発に議論していますよね。日本ではあまり考えられない文化だなぁと思いました。
議論を乗り越えて一緒に生きていこう、と社会で共存することを学んで欲しい
セルヴォニ先生
フランスは宗教を学校教育に取り込んではいけません。それに関しては厳しいルールがあるのです。でも実際の子どもはみんなそれぞれに宗教を持っているから、学校の講義を無宗教で教えても通用しないのです。だったらそれぞれの宗教について議論させて考えさせる方がよほど意味があるはずです。その議論を乗り越えて一緒に生きていこう、と社会で共存することを学んで欲しいと思っています。
異なる文化や価値観があることを学び、共にフランス社会で生きていく子どもたち
ヴェルトゥチェリ監督
昔のフランスでは、先生が上から目線で講義をするのが当たり前でした。ただ、最近は子どもたち同士が話し合って学んでいくという風に変わってきました。『バベルの学校』で観れるレベルの議論をするのは実際とても大変です。あの適応クラスは素晴らしい環境でした。一般的に、アングロサクソンの子どもは自己主張することに慣れていますが、アジア系の子どもはおとなしい。アジア系の子どもにとって、自分のことを皆の前で話すのはとてもプレッシャーを感じます。しかし、実際に話してみて、他人が自分のことをわかってくれるというのを経験すると、連帯感や友情が生まれます。また、生徒同士の議論や先生に対する反論などは、その過程で自分の問題として捉え、考えも深まりより良い学びとなるはずです。
れみ
いろんな異文化に日々接している先生や監督の、理想のライフスタイルってありますか?または人生で大切にしてるものとか価値観とか。何か読者にアドバイスをお願いします。
偏見を持たない、そこでジャッジメントしない
セルヴォニ先生
アドバイスですか?難しいですね(笑)。強いて言うなら、出会いを大切にすることですね。異文化や他者との出会い、それを共有してお互いに良い相互作用を生み出すこと。例えば旅をして世界を見たりする中で、そこで出会う何かによって何かが生まれるかもしれません。もちろん自分の国にいても異文化との出会いはありますよね。あとは好奇心を大切にすることですね。それから寛容さですね。偏見を持たない、そこでジャッジメントしないというのは大切にしています。
れみ
監督は何かありますか?
最近の人たちはエゴイズムに傾いて、自分の世界を大切にしてばかり
ヴェルトゥチェリ監督
言いたいこと言われちゃった(笑)。私も同じです(笑)。あと愛ですね。他人の立場に立って考えるということはとても大切だと思っています。自分がその立場だったらどうなるかを想像する。きっと手を差し伸べられることを願うはずです。フランスに限らないかもしれませんが、最近の人たちはエゴイズムに傾いて、自分の世界を大切にしてばかりです。隣の人に手を差し伸べることを学ぶ必要があると強く思っています。
ヴェルトゥチェリ監督と
れみ
監督、何か最後にありますか?
ヴェルトゥチェリ監督
そうですね。あの適応クラスの子どもたちはみんなフランスで学業を続けていますが、3人は母国に帰りました。神様の問題を語ってた子はサウジアラビアに。あとはアイルランドとイギリスに帰った子がいます。今回撮影した適応クラスの子どもたちの将来が楽しみなので、是非10年後に彼ら彼女らが今どうしているかというのを追いかけたドキュメンタリー映画を作りたいですね。
れみ
監督、先生、お忙しい中どうもありがとうございました。
2015年 1月31日(土)
新宿武蔵野館、渋谷アップリンクほかロードショー