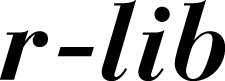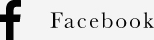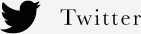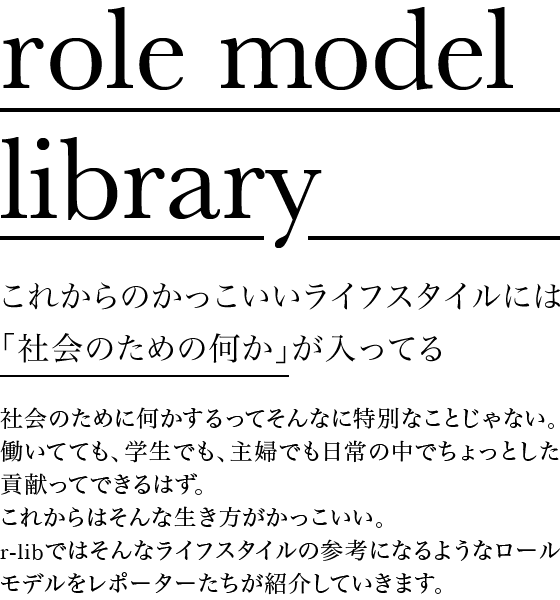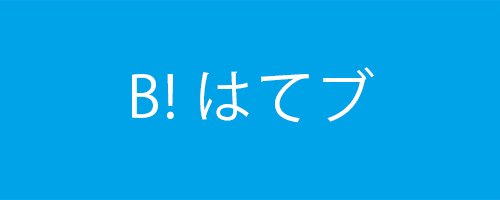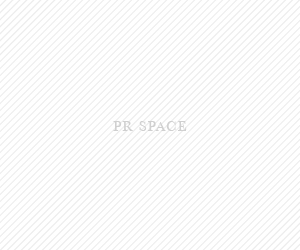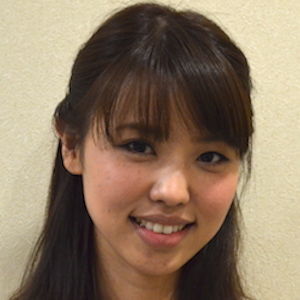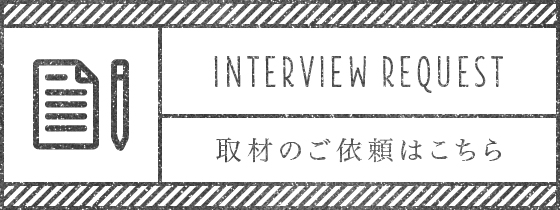先日、職場のウェブサイトのほうで記事を書きました。
たくさんの方に読んでいただいて嬉しかったものの、
あの原稿は、ちょっと無理に「オチ」をつけたようなものだった、
ということを、ここにこっそり懺悔しておきます。
私は、自分が担当している東エルサレムの事業が大好きです。
改善できる部分も多々ありつつも、「正しい」方角を目指していると思います。
だから、締めに書いた事業への気持ちは、全く嘘ではありません。
ただ、近所の少年とのやり取りを経て強まったのは、
事業への思いだけではなかったのです。
彼が「ユダヤ人をよく殺ってくれた」と殺人犯を讃えたのを聞いたとき、
そして「暴力には反対よ」と答えた私に
「お姉さん、いったいどれくらいパレスチナにいるの?」
(=それで、どれだけパレスチナ人のことが分かったつもりなの?)
と彼が言葉をぶつけてきたときに、
自分が強烈に感じたものが、他にもありました。
それは、彼らが私に対して抱く異物感の存在。
自分の存在が、ここで如何に「ヨソモノ」であるかということ。
そして彼らから見たときに、
私がどれだけ「きれいごと」を振りかざしているのかということです。
元々、頭で分かってはいたのです。
多少のアラビア語を喋ろうが、誰かの家に足しげく通おうが、
現地の人と同じ釜の飯を食べようが、同じ目線に立とうと努力しようが、
私は日本で身につけたものを引きずっています。100%の当事者にはなれません。
それで、いいんです。
当事者だけでは解せない何かがあるからこそ、ここには外部者が必要で、
私は外部者として「適切な」距離を取りながら、
当事者の手の出せないところに働きかけるのが仕事であるはずだから。
それでもひとたび何かが起これば、
私が彼らに提示することは、やっぱり「きれいごと」に過ぎなくて。
日頃は仲が良かったとしても、こういうときには明確な線引きが
私たちの間に立ち上がるような気がします。
そうすると、
「そんな噛み合わない状況で、また大きな暴力を止められない状況で、
いったい私はここに居ていいんだろうか」
と、どうしても思ってしまうのです。
正しい答えなんて、無い問いです。
そこに、「原稿読んだよ」というラオス駐在の先輩から
タイムリーなメッセージが届きました。
「きれいごとを言い続けるのが、第三者の役割だ」
「この暴力はいい、この暴力は悪い、という情状酌量に拘泥するのは、
当事者はともかく、外部者には危険すぎる」
「だったら、きれいごとを言う価値はあるだろ。
きれいごとしか普遍性をもてないこともあるんだから」
そう、ですかね。そうなのかな。
悩みは尽きませんが、少しほっとしたような気もします。
現場ならではの、贅沢な悩みです。もうしばらく抱えて、温めてみます。

(村に行けばそこら中に転がっている、暴力の形。)